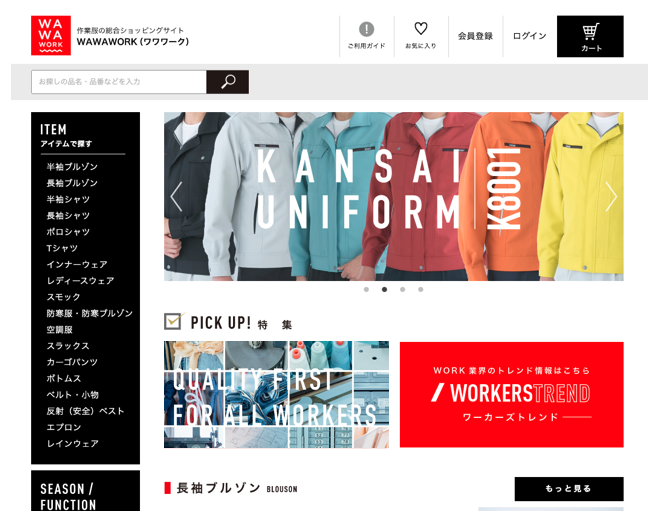業務用と家庭用エプロンの、実用性と機能性の違い、言えますか?
2019.11.08
カフェやレストラン、ファストフードなどの飲食店やスーパーや小売店、さらに市場、保育施設や介護施設など、街中でよく目にするエプロンは、私たちにとってとても身近な作業着といえるでしょう。家庭でも料理、家事、DIY、ガーデニングなどをする際、男性、女性を問わず身につけることが多いエプロンですが、ひと昔前までは「お母さんのユニフォーム」と、エプロンをとらえていた人も多いのではないでしょうか。
家庭や仕事場、趣味や学校、イベントなどの幅広いシーンで着用されるエプロンは、デザインや種類も豊富。子どもからおとなまで、性別・年齢を問わず広く使用され、機能性やファッション性も多様化しています。
今回は、私たちがシーンや目的に合ったエプロンを選ぶヒントとなるよう、業務用エプロンと家庭用エプロンの違いをはじめ、その種類や機能性などをご紹介していきましょう。
まずは、子どもの頃から慣れ親しんでいるエプロンが、いつ頃、どこで生まれ、どのように発展したのか。その歴史からたどっていきましょう。
エプロンはもともと権威の象徴だった!?
エプロンの起源は、はるか紀元前にまでさかのぼるといわれています。
古代、エジプトをはじめクレタ島、南米、中国などでは、壁画や彫像に神々や神官などがエプロンを身につけた姿で描かれています。なかでもエジプトの壁画や彫像では、ごく薄い麻布をたたんだ三角形のエプロンを身につけた当時の人々の姿が数多く確認できますが、これは儀式用の装束として権威を象徴するものだった、とされています。
現代に生きる私たちがあたりまえのように身につけている布地は、産業革命以前にはとても稀少なものでした。そのため、中世以降のヨーロッパでは、腰まわりに不要な端布(はぎれ)を巻くなどして、人々は貴重な財産である衣類を保護していたのです。
職種別エプロンへと発展。食肉店のエプロンはなぜストライプ?
やがて、こうした端布が「実用的な仕事着」としての位置づけで改良されていきます。さらに、さまざまな職種間の分業が進むにつれて、それぞれの職種を代表する特有のエプロンとして発展していきます。その過程で、職人全般を「エプロンをした男たち = エプロン・メン(Apron men)」と呼ぶようになり、それぞれの職種と特有スタイルのエプロンが強く関連づけられるようになります。
代表的な職種別エプロンとしては、主に以下が挙げられます。
●レザー・エプロン:鍛冶、石工
●チェックド・エプロン:理髪師
●グリーン・ベイズ(粗いウール地)のエプロン:家具運搬人
●ブルー・エプロン:手仕事による職人
●白とブルーのストライプのエプロン:食肉店

それにしてもなぜ、食肉店のエプロンがストライプ柄なのか疑問を抱きますね。実は、これにはしっかりした理由があるのです。
紺地に白の線が入ったデニム生地とされるヒッコリー(hickory)やストライプは、汚れが目立ちにくいメリットから、作業着のオーバーオールや大工職人のパンツ等に使用され、その利点から英国では作業着の定番柄になっていました。なかでも、ストライプの代表格とされるのが「食肉店のストライプ柄エプロン」です。
今から180年以上前、ロンドン中心部に位置する精肉市場「スミスフィールドマーケット」の作業着として、ラッシュブルックス製のストライプ柄エプロンが生まれたとされています。その後、長い歳月を経て、現在では英国の精肉店スタッフをはじめ、レストランのシェフ、料理番組に出演する著名なシェフたちの御用達とされるワークウエアに位置づけられていきます。
古くから精肉店で働く人は、ゴム仕様のウエストでベルトを必要としないダボッとしたシルエットの、ストライプやチェッカーなど色柄が豊富なパンツを履き、さらにその上に、ストライプ柄のエプロンを身に着けた人々が立ち働いていました。これは食肉加工の際に付着する油分や血による汚れが目立たない実用的なメリットがあったからといわれています。そうした光景をイメージすると日本の厨房でよくみかける景色とはまた異なる、ヨーロッパならではのセンスや特色がうかがえますね。
ちなみに、ストライプやチェッカーなど色柄が豊富なパンツは「シェフパンツ」と呼ばれ、デザインや色合いのおしゃれさから、2018年くらいから日本の街のあちこちで、大胆な色・柄をあしらったシェフパンツのアレンジバージョンを見かけるようになっています。
装飾品としてのエプロン。王妃のエプロンにはダイヤモンドや真珠が!
ルネサンス期(14~16世紀)に入ると、紡織技術の向上を反映して、上流階級の女性にファッショナブルな衣装が普及し始めますが、当時の装束は一般的に裾が長く、袖が着脱式になっていました。こうした衣装の汚れよけに、洗濯しやすいエプロンが流行することになります。
女性が多く身につけていたこのエプロンは、職人用の男性向けエプロンとは異なり、胸当てのない腰まわりに着用するものがほとんどでした。さらに16世紀に入ると、エプロンにはレースや刺繍で装飾がほどこされるようになり、なかでももっとも豪華とされたのが、フランスの王妃カトリーヌ・ドゥ・メディシスが愛用していたエプロンといわれます。王妃だけあり、そのエプロンにはダイヤモンドや真珠が2000個あまりもちりばめられていたというから驚きです。
そして、産業革命により紡織が機械化されると、上流階級のものだったエプロンは市井(しせい)の女性たちの間にも広まり、さまざまに意匠をこらしたエプロンが普及していきます。やがて、こうした仕事着としてのエプロンは、立場により使い分けられるようになりますが、それは例えば、上流階級の奥様などが着用したシェニール糸と呼ばれる玉虫色のシルクで縁取ったサテン地のエプロンもそのひとつでしょう。あるいは、下働きの女性たちはリンネル地の無地のエプロンドレスというように、仕事着としてのエプロンは職務内容と身分によって、その材質や装飾に厳格な区別が付けられていました。やがて、清潔さを保つための必需品となった実用的エプロンは、メイドやハウスキーパーの定番ユニフォームとなっていきます。
そういえば、ヨーロッパの民族衣装にはエプロン仕様のものも多いことに気づかされますが、それにしても、エプロンが他者に見せるための「装飾品」と、実用的な「作業着」としての二面性を保ちながら、発展した点は非常に興味深いですね。

日本のエプロンといえば、そう割烹着と前掛け!
日本では、明治・大正期に欧米文化の流入とともに、「洋装前掛け」「サロン」と呼ばれるものが誕生しますが、戦前はまだ和装も多かったため「割烹着(かっぽうぎ)」や「前掛け」が主流でした。
割烹着とは、着物の上からつける袖つきのエプロンのこと。着物をすっぽりと包み込むことで着物に付着する汚れを防ぐ機能をもっています。
一方の前掛けとは、厚手の綿素材でできた腰に巻くエプロンのようなもの。お店の店名やロゴマークが入っていることも多く、その店舗の作業着としてスタッフ全員で身につけることも多いですが、そういえば『サザエさん』に登場する「三河屋」さんも前掛けを身につけていますね。
オリンピック景気に代表される昭和40年代に入った経済成長期の日本では、国民の生活スタイルの変化に伴い、女性の間でミニスカートブームが起こり、一般家庭でも洋装が定着したことからエプロンブームが起こります。ブーム到来によって、日本の女性の間では着物の上に羽織る白い割烹着から一転、海外から輸入されたファッション性の高いおしゃれなエプロンが人気を博し、「実用的な作業着」から「おしゃれなホームウェア」へと変化をとげていくことになります。

エプロンを「着る理由」は何なのだろう?
さまざまな変化を経て、日本人にとって身近な存在となったエプロンですが、そうはいっても、現在においてもただなんとなく習慣で身につけている人も多いのではないでしょうか。
エプロンを選ぶ際には、デザインや価格以上に、エプロンを「着る理由」や「種類」「機能」「お手入れの方法」などを押さえておきたいもの。まずは、エプロンを「着る理由」は何なのかについて考えてみましょう。ここでは、その理由の主なものを挙げていきましょう。
●衣服が汚れないようにする
●衛生面から、汚れればすぐに取り換えられる便利さがある
●肌への汚れやケガを防ぐ機能がある
●胸や腰にポケットがついているものも多く、収納力が高い
●制服としての、ビジュアル的な統一感
●タオルや手ぬぐいの代わりになる
この他にも、エプロンを着用することで「作業」や「仕事」に気持ちを切り替える、あるいはモチベーションを高めるという二次効果もあります。
さまざまな仕様に分けられるエプロンの種類
エプロンは主に、大きく「胸当てエプロン」と「腰エプロン」に分かれます。「胸当てエプロン」は腰か首にひもを通し、上半身から下半身までをカバーするエプロン。腰エプロンは腰から下のみをカバーするエプロンです。
ここでは、「胸当てエプロン」と「腰エプロン」を比較してみましょう。
【胸当てエプロン】
●汚れをガードできるのは、主に腰から胸までの上半身
●ファッション性よりも機能性重視
●使用される主な業務内容は、外仕事、水仕事、軽作業など
●主な業務や目的は、キッチンスタッフ、清掃業、倉庫作業、ガーデニングなど
【腰エプロン】
●汚れをガードできるのは下半身のみ
●機能性よりもデザイン性重視
●主な業務は、接客業や飲食店のホールスタッフ
また、腰エプロンは胸当てエプロンよりも、おしゃれ度が高いとされます。
飲食店を例にあげると、下記のように使い分けることができます。
〇胸当てエプロン:調理などで上半身が汚れやすいキッチンスタッフ
〇腰エプロン:メニューを運んだり接客するホールスタッフ
ギャルソン、ソムリエ専用エプロンも

胸当てがなくウエスト部分から足にかけて巻くタイプのエプロンは「サロンエプロン」と呼ばれます。あるいは、フランスのカフェの給仕(ギャルソン)が着用していたことからギャルソンエプロン、ソムリエエプロンと呼ばれることもあります。
最近ではカフェやレストランでユニフォームとして見かけることが多くなりました。今では、サロンエプロンをしてシャツを見せるのが飲食店のホールスタッフのファッショントレンドだそう。店のスタッフがどのようなシャツを着て、どのようなエプロンをしているのか、見比べてみるのも楽しいですね。
さらに面白い点は、腰エプロンの腰ひもをギュッと締めることで、骨盤、丹田(たんでん=へその下部分)が適度に圧迫されることから、腰痛防止を助ける効果がある、とされる点です。前にご紹介した「前掛け」は、昔から酒店や米店でも使われていましたが、酒や米などの重量物を運ぶ際に腰を傷めない……という隠された働きもあったのですね。こうした知恵を見習って、台所に長く立っていると腰が痛くなる人は、腰エプロンを試してみるのもよいかもしれません。
たすき掛け(X型)エプロン

では次に、胸当てエプロンの種類をみていきましょう。大きく分けて3種類あります。
最初は、背中のひもがたすきのようにX型になっているエプロンについてです。
【たすき掛け(X型)エプロンのメリット】
●腰でひもを結ぶため、シルエットがきれいに、細く見える
●ほどよい締めつけ感があり、着心地に安定感がある
●自分のウエストサイズに合わせることができる
●他のエプロンよりバリエーションが多い
【たすき掛け(X型)エプロンのデメリット】
●肩にひもを通しているため、肩こりを起こしやすい
●毎回ひもを結ぶ必要があるため、着脱が面倒
●片方の腕を上げた際に、反対の肩ひもがズレる可能性がある
H型エプロン
背中のひもがH型で基本的に腰ひもがなく、ボタンで留める仕様になっているエプロンです。
【H型エプロンのメリット】
●ひもを通す必要がなく、そのままかぶって着用することができる
●肩ひもがずれにくい
●肩ひもが太めになっているものが多く、体への負担が少なく着心地がよい
●たすき掛けエプロンよりも肩がこりにくい
【H型エプロンのデメリット】
●ひもではなくボタンで留めているため、ストンとしたシルエットとなりラインが太く見える
首掛けエプロン

首掛けエプロンとは、首ひもと腰ひもで留めるタイプのエプロンのこと。
【首掛けエプロンのメリット】
●腰ひもを結んで着用するため、細くスッキリした印象を与える
●首にひもをかけるので肩ひものズレがない
【首掛けエプロンのデメリット】
●ひもを首の前から掛けているため、肩と首がこりやすい
たすき掛け(X型)エプロン、H型エプロン、首掛けエプロンのメリットとデメリットをご紹介してきましたが、いずれもさまさまな違いが見受けられますね。実際にエプロンを選択(購入)する段階では、次のどのコンセプトを優先するかによって、選択するとよいでしょう。
●つけたり外したりすることが多い人では、簡単に着脱できるもの
●肩こりや腰痛など体の負担を少なくしたい人は、着心地に安定感があるもの
●シルエットをすっきりと美しくみせたい人は、腰ひもを結ぶタイプのもの
●汚れの付着が気になる人は、洗濯しやすく、汚れが目立たない色・柄のもの
エプロンの素材の種類と違い
エプロンによく使用される素材の代表選手は「ポリエステル」と「綿」ですが、それぞれどのような特徴があるのでしょうか。
【ポリエステル素材のメリット】
●防汚 (ぼうお)、撥水(はっすい)、撥油(はつゆ)などの機能性に優れている
●濡れた時も洗濯後も速乾性が高く乾きやすい
●シワになりにくく、型くずれしにくい
●工業用の洗濯にも適応できる耐久性がある(スタッフのエプロンをまとめてクリーニングできる)
【ポリエステル素材のデメリット】
●ポリエステル混率が高いほど、テラテラした特有の光沢感が出る
●熱に弱く、燃えやすい
●静電気を帯びやすい
●通気性や吸水性が悪いため、ムレやすい
●汚れが落ちにくい
【綿素材のメリット】
●ポリエステルに比べて火や熱に強く、燃えにくい
●柔らかく肌ざわりがよい
●相手や周囲に自然で親しみやすい印象を与える
●吸水性がよい
●プリント加工が容易なため、デザイン性に優れたものが多い
【綿素材のデメリット】
●ポリエステルに比べ耐久性がなく、洗濯するうちにヨレたり縮んだりする
●シワになりやすいため、アイロンがけが必要になることも
●色落ちや色あせしやすく、生地が経年劣化する
なかでも火を使う作業の場合、エプロンが燃えやすいか燃えにくいかはとても重要な選択基準になるため、キッチンでの仕事がメインの場合であれば、綿素材のエプロンを選ぶようにしましょう。また、エプロンを使い続ける場合には、手入れのしやすさもエプロンを選ぶ基準として大切なポイントになります。購入時にはシワになりやすいか、なりにくいかなどを含めて、素材の特徴を押さえておきたいものです。
業務用エプロンと家庭用エプロンの違い
では次に、業務用エプロンと家庭用エプロンの違いを比較しましょう。
【業務用エプロン】

●ハードなシーンでの使用が想定されるため、メーカーごとに厳しい耐久試験が行われ、高い耐久性を備えているものが多い
●機能性に特化したポリエステル混率の高いものが多く使われている
●汚れが目立ちにくい、濃い配色を採り入れていることが多い
●どんなユニフォームにも合わせやすいよう、無地のものが多い
●頻繁にクリーニングに出しても、洗濯頻度が高くても劣化しにくい
●ペン、小物、オーダーを取る端末などの持ち運びを考慮し、ポケットのサイズや位置が機能的に設定されている
【家庭用エプロン】
●おしゃれなデザインやカラフルなプリント、ナチュラルテイストなリネン系など、ファッション性の高いものが多い
●ハードなシーンでの使用を想定しないため、ポリエステルよりも耐久性の低い綿素材のものが多い
ここまでご紹介した通り、最大の違いは耐久性となります。業務用は耐久性に優れていることが多く、加えて機能性が重視されます。一方の家庭用は、デザイン性重視がポイントになるようです。ただし、家庭で使う際も、使用頻度が高く、丈夫で洗濯に強いエプロンを希望する場合は、業務用エプロンも選択肢に入れて選ぶとよいでしょう。
多彩な機能が備わっているエプロン
実は私たちが想像する以上に、エプロンには多彩な機能が備わっていることをご存じでしょうか。ここからは、さまざまな機能性についてご紹介していきましょう。
【水・油をはじく機能】
エプロンの汚れで多いものが水と油。その汚れ付着を防ぐのが「撥水(はっすい)」「撥油(はつゆ)」機能です。
〇撥水加工:水分をはじき、汚れても水洗いで簡単に落とすことができる
〇撥油加工:油や油性の汚れをはじき、しみこませない
【静電気を防ぐ機能】
冬の乾燥している時期などに着用すると、エプロンは静電気を帯電しやすくなります。エプロンが帯電しているとバチバチ静電気が起こったり、衣服とエプロンがまとわりついて、作業をする上でわずらわしさを感じることがあります。
また、空気が乾燥している時期はホコリやチリも衣類に付着しやすくなります。店舗のスタッフが見た目に不潔な感じのエプロンを身に着けていると、お客様に不快感を与えかねません。こうしたデメリットを鑑(かんが)みて、業務用エプロンの多くには制電機能が備わっていることが多いので、購入時にはその点にも注意してみましょう。
〇制電加工:衛生面を重視するプロ用エプロンで最も多く加工されている機能。衣服のまとわりつきの原因になる静電気をおさえ、チリやホコリの付着を防ぎ、清潔感を保つ。
【落ちにくい汚れを防ぐ機能】
エプロンはそもそも衣服への汚れ付着を防ぐ目的をもったものですが、エプロンそのものも清潔に保っておきたいもの。汚れた状態のまま身につけていると、細菌が繁殖する可能性なども考えられ、衛生上好ましくないので、汚れた場合はすぐに取り替える、あるいは、1日ごとに取り換えるといった交換頻度を保ち、その都度、洗濯する必要があります。洗濯する際も、油、血液等の落としにくい汚れが付着した場合は特に、漂白剤につけおきする、あるいは汚れに応じた専用洗剤を使って洗浄する必要があります。
こうした特徴から、エプロンを清潔に保つ機能として「防汚(ぼうお)」機能や「退色」機能が備わったものもあります。
〇防汚(ぼうお)加工:一度つくと落ちにくい汚れやチリの付着を防ぐ
〇退色加工:塩素系漂白剤による色あせを防止する
【収納機能】
作業着としてのエプロンは、仕事場でも家庭でも仕事や作業に必要な道具や小物、ペンやメモ、携帯等の端末など、ポケットの数や収納スペースの多さも重要になります。道具や小物がとっさに必要になった時に収納機能が備わったエプロンを身につけていれば、あわてずスムーズに必要な道具や小物を取り出すことができます。

ふだん、何気なく眺めたり着用する機会の多いエプロンですが、形や生地の素材、色や機能などにさまざまな違いや意味があり、工夫がこらされていたことがおわかりいただけたでしょうか。飲食店、スーパー、商店などで、それぞれどんなエプロンが使われているのか、比較してみると新たな発見があるかもしれませんね。
カフェブームともいえる昨今、パリッとのりが効いたシャツに、エプロンをまとうおしゃれなユニフォームに憧れて、カフェで働きたいという人も増えているようです。また、料理を得意とする男性も増え、男性用エプロン(メンズエプロン)も多種多様なものが流通しています。そうした社会的変化を受けて、最近では男性へのプレゼントとして、エプロンは人気急上昇のアイテムだそう。さらに、ホームパーティなどに招かれた時、そのご家庭のカップルや夫婦がお揃いのエプロンで料理している姿は、とても素敵ですよね。
カフェエプロン、ウエストエプロン、ショートエプロン、ワークエプロン……デザインも呼び名も多様化する一方のエプロンですが、流行や見た目だけでなく、エプロンを着る目的とシーン、必要な機能などを検討したうえで、とっておきの一枚を選んでみてはいかがでしょうか。

作業服、ユニフォームを買うならWAWAWORK(ワワワーク)
WAWAWORK(ワワワーク)は、日本最大級の作業服の通販サイトです。
WAWAWORK(ワワワーク)では、オシャレでかっこいい最新の作業服・作業着・ワークウェアから、機能的で便利な定番のワークアイテムまで、幅広い品揃えの商品を激安特価でご提供しているほか、刺繍やオリジナルロゴ入り等のカスタムも対応しております。
作業着、ユニフォームをお探しであれば、通販サイトWOWOWORK(ワワワーク)をぜひご覧ください。webサイト:https://wawawork.work/