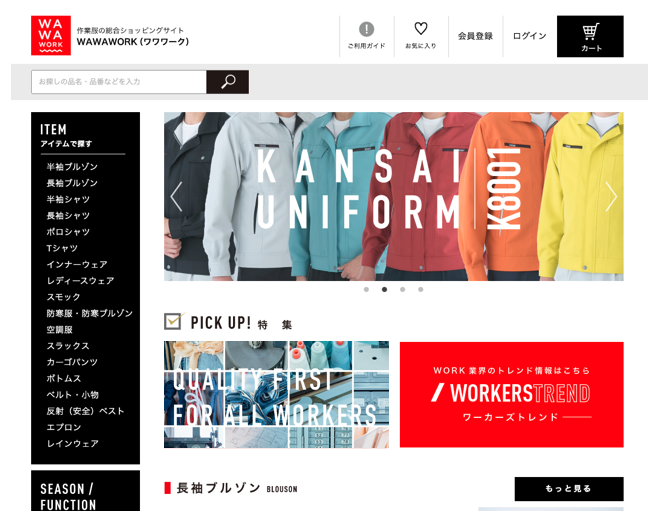伝統とバイオテクノロジーの共演!最高に旨い酒の開発に心血を注ぐ「杜氏」
2019.11.18
近年、来日外国人観光客の増加によって、あらためて日本文化の継承者である「職人」に注目が集まっています。テレビ等のマスメディアだけでなく、多種多様な情報ツールで職人、匠、エキスパートと呼ばれる専門職の人々の活躍が取り上げられ、たとえその世界に精通していなくともニッポンが誇る匠の技を知る機会が増えてきました。
蔵人(酒職人)の統率者「杜氏(とうじ・とじ)」もそのひとつでしょう。昨今の日本酒ブームの影響も相まって、国内外から杜氏に熱い視線が向けられています。
また、杜氏は「酒造家」「酒造作家」とも呼ばれており、海外の人々の多くにとっては、芸術の領域といえる日本酒を扱う芸術家、創作家としてとえられているようです。
それを証明するように、銘酒、名酒と呼ばれる日本酒を手がけた杜氏の熱い思いや酒造りに懸ける情熱を聞けるイベントが人気を集めていて、そうしたイベントでは日本酒にとどまらず、造り手である杜氏がどのようなコンセプトやテーマをもってして酒造りに携わっているかについても、聴講者は高い関心をもって耳を傾けているようです。
杜氏と日本酒の文化と歴史をご紹介した前記事に引き続き、今回は伝統とバイオテクノロジーの結晶である、日本酒の開発に情熱を傾ける杜氏の姿にスポットをあててご紹介することにしましょう。
“酒の神様”という異名を持つ「杜氏」とは?
有名な杜氏は日本にたくさんいますが、たとえば「日本四大杜氏」のひとつに数えられる石川県の「能登杜氏」で、四天王のひとりとされる農口尚彦(のぐちなおひこ)氏をご存じの方も多いのではないでしょうか。
1932年生まれの農口尚彦氏は、酒造界において“酒の神様”と呼ばれ、ほかの四天王の3人にも酒造りを指南した“匠中の匠”と言われる存在です。農口氏の功績をご紹介すると、その華々しい功績がうかがえます。
●1990年/JAL初のファーストクラスに搭載する日本酒(菊姫の大吟醸)の杜氏
●2006年/「卓越した技能者表彰制度」において厚生労働大臣が表彰する「現代の名工」に認定
●2008年/「黄綬褒章」受章
農口氏の功績は、2010年、2014年に放映されたNHKのドキュメンタリー番組等でも取り明げられていることから、杜氏の中でもその認知時は群を抜いて高いのですが、82歳で一度は引退したものの、2年後の2017年に復活。驚くべきは、内外からの期待に応えるべく、84歳で酒造メーカーを設立したという心身ともに強靭なバイタリティにあります。
2003年にポプラ社から刊行された農口氏による著書『魂の酒』には、氏が培った技術を継承しながらも「新しい酒」に挑戦する意気込みが随所にちりばめられており、日本酒がまだまだ未来への可能性を秘めていると示唆する言葉の数々は、説得力に満ちています。
つけ加えると、農口氏の酒造メーカーのコンセプトは、
《農口尚彦杜氏の酒造りにおける匠の技術・精神・生き様を研究し、次世代に継承すること》 (出典:農口尚彦研究所)
このコンセプトを拝借すれば、職人の生き様とは、それまで培ってきた高い経験値と感性であり、それをいかに酒に反映させるかが杜氏の技ということになるでしょう。
それだけに蔵人となって経験を積めば、いずれは誰もが杜氏になれるわけではありません。伝統的な技法と最新技術が融合した日本酒の製造方法は、世界に多くのアルコール類がある中で最も複雑であり、緻密な作業が求められる世界といわれています。
それゆえに、蔵人を管理するマネジメント力や統率力といったリーダー的要素から、さまざまな変化を的確に察知し、その変化に応じて、経験則に則った職人としての判断力や対応力、ものづくりに従事する者としての年間を通した生産管理力など、多面的な総合力が求められます。そうした総合スキルが備わってこそ、日本酒造りのエキスパートたる人格が培われ、周囲の人々からの人望につながり、ひいては美味しい日本酒を生み出すことになるのでしょう。
日本酒の開発に欠かせないバイオテクノロジー

酒造りにおいて、バイオテクノロジーに関する知識や経験則を高めることは不可欠ですが、そもそもバイオテクノロジーとは何を指すのでしょうか。ここではそのキホンについてご説明しましょう。
1980年頃から使われだした単語「バイオテクノロジー(biotechnology)」は、「バイオロジー(生物学/biology)」と「テクノロジー(技術/technology)」の合成語。生物の生命現象を有用に利用するための技術の総称となります。
今日では非常に幅広い領域で活用されているバイオテクノロジーですが、近年において認知されているものを挙げると、「遺伝子組換え技術」や「細胞培養技術」を利用した農作物や医薬品などが、よく知られています。
また、廃水処理や難分解性化合物※を微生物を活用して分解させる環境保全など、日常生活に密接にかかわる領域のみならず、地球の人類すべてに密接にかかる技術として、バイオテクノロジーは大きな注目を集めています。
そうした点から、昨今大きな注目を集めるバイオテクノロジーですが、実はバイオテクノロジーが定義されるはるか昔の紀元前から、人類は経験と知恵によって塩辛、豆腐よう、なれずし、くさや、魚の糠漬けなどの保存食や、キムチ、みそ、納豆、ヨーグルト、酢、みりんなどの発酵食に、この技術を活用してきました。
※難分解性化合物とは、この化合物が地球の環境中に放出されると、分解されずに環境中に残留されるもの。代表的な化合物としてDDT、PCB、ダイオキシンなどが挙げられる。環境中に残留することで、人の健康や生態系に大きな影響をおよぼす。
二つの化学反応によって生産される、日本酒のアルコール

日本は世界有数の発酵食品大国で、日本酒をはじめ醤油や味噌、納豆、鰹節などの発酵食品をいにしえから製造してきました。発酵とは、微生物のはたらき(繁殖)によってデンプンやタンパク質、ブドウ糖などが分解され、炭酸ガス(CO2)やアルコール、アミノ酸などが生成される化学反応を指します。この作用によって発生する微生物には幾多もの種類があり、食品によって使い分けられられています。
幾多もの種類がある微生物は、大まかに以下の3つに分類されます。
●「カビ」➡ 醤油・味噌・鰹節などの製造に活用
●「酵母」➡ パン・ワイン・ビールなどの製造に活用
●「細菌」➡ 納豆・漬物・くさやなどの製造に活用
日本酒は、カビの一種の「コウジカビ」とも呼ばれる「麹菌(こうじきん)」と、酵母の一種である「清酒酵母」を用いて発酵させますが、この二つを用いることこそが、日本酒における発酵の特色となっています。
アルコール発酵は、微生物が糖を分解することによって進みますが、日本酒の原料の米には糖分が含まれていないため、発酵ができません。 そこで、麹菌(アミラーゼ)で米のデンプンを糖分(ぶどう糖)に変え(糖化)た後、清酒酵母によりアルコール発酵を行います。この「糖化」と「アルコール発酵」の二つの化学反応を同じタンクで同時に行う発酵技術を「並行複発酵」といい、この発酵技術は、東アジア特有の高度な発酵手法なのです。
日本独自の味覚「旨味」は、麹が生み出すアミノ酸
日本酒の味わいを構成している味覚のひとつが「旨味(うまみ)」ですが、和食はこの旨味なくして、その豊かな味わいが完成しないといわれます。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで、甘味、塩味、酸味、苦味といった基本とされる味に加えて、「UMAMI」と表記された日本独自の味覚に世界から大きな注目が集まるようになり、いまや「UMAMI」は世界共通語になっているほどです。
この旨味の代表的な成分は「アミノ酸系物質」「核酸系物質」「有機酸系物質」の3つであり、昆布や干しシイタケなどに多く含まれていることが知られています。日本酒では麹からこのアミノ酸が生成され、独自の旨味を生み出します。
麹菌は、酵素生産能力が高く、酵素を体外に分泌してデンプンをブドウ糖に、タンパク質をアミノ酸に分解します。それゆえ、日本酒の旨味は“麹が肝”だといわれていて、杜氏は特にこの工程に注力するといわれています。※蒸米上で麹菌を育てることを「製麹(せいぎく)」といいます。
また、日本酒にはアルギニン、チロシン、セリン、ロイシン、グルタミン酸など約20種類のアミノ酸が含まれますが、これを他の酒類に含まれるアミノ酸量と比べると、一般的なビールの8倍、ワインの2.5倍ほどにおよぶといわれています。この数値からも、おいしい日本酒ほど「UMAMI」が溶け込んでいることがわかります。
しかし、アミノ酸が多ければ多いほど上等の日本酒になるか……というと、決してそうではありません。アミノ酸が多ければ味はしっかりと濃くなり、少なければ味はすっきりとして淡麗になります。しかし、多すぎれば“くどさ”と“雑味”が出てしまいますし、少なすぎても“そっけなく”“物足りなさ”を感じる味わいになってしまうことになるのです。
したがって杜氏は、しっかりとした力強い味わいの日本酒にするのか、淡麗という言葉で表現される味わいの日本酒にするのか、その酒のコンセプトに沿って、製麹の培養を調整するのです。この調整は、微妙な環境変化の中に存在する生きた麹菌を扱う難しさもあって、温度管理などさまざまな変化を鑑みた微妙なさじ加減はもちろん、長年の経験による的確な判断力といった熟練技が必要とされます。
私たちが普段味わっている日本酒。その透明な液体には、酒造りのエキスパートたる経験値と、最新のバイオテクノロジー技術が溶け込んでいることになり、杜氏なくして美味しい日本酒を継続的に堪能できない、といえるのです。
いくつもの工程を織り重ねて生まれる日本酒

酒造りは、複雑な工程を経ながら、ひとつひとつの工程が慎重に行われていきます。蔵元によって各工程の手法や分量が異なる場合もありますが、酒造工程の大まかな流れは以下の14工程になります。
工程①/精米
酒造りにおいては、私たちが普段食べている白米ではなく、酒造り専用に開発された「酒造好適米」が主に用いられます(一般的には酒用の米という意味で「酒米」と呼ばれる)。酒米に求められる特性は、主に「大粒」「心白の割合が大きい」「低タンパク」の3つとなり、その理由は以下のとおりです。
●大粒 ➡ 精米度を高めることが容易。
●心白の割合が大きい ➡ 心白とは、白く不透明な米の中心部分のこと。タンパク質が少なく密度が粗いため吸水しやすく、麹菌を米の中心まで均一にいき渡らせやすい。
●低タンパク ➡ タンパク質は水に溶けにくく、米の吸水性低下やデンプンの膨潤(ぼうじゅん)・糊化(こか)を抑えてしまう。高タンパクではアミノ酸が過剰に生産されてしまうため、酒の雑味につながる可能性がある。
工程②/枯らし
精米したての米は、精米時の摩擦によって熱を帯びています、また、米の表面と中心の水分量が均一でなくなるため、表面のみ水の給水速度が加速し、すぐに洗米して水を加えると、米が割れる危険性がある。こうした理由によって、精米して熱を帯びた米を冷暗所で2~3週間寝かせて(鎮静させて)、米の水分量を安定させる。
工程③/洗米
米についている糠(ぬか)を水で洗い落とす。私たちがご飯を炊く際に米を洗うことと同じ作業を経る。このとき水流を利用した洗米機を活用するなど、米を傷つけずムラなく洗えるような工夫が必要とされる。
工程④/浸漬(しんせき)
米に適当な水分を吸収させる。数分から数時間と蔵元によって浸漬の時間は異なるが、酒造りに必要な適量な水分を含ませた後、水切りする。
工程⑤/蒸米
米を炊かずに蒸すのは、麹菌が繁殖しやすい水分量にするため。蒸米は「麹用」「酒母用」「掛け米用」に分けられ、それぞれの適切な温度に冷ます(放冷)。
工程⑥/製麹
麹菌を米に振りかけて付着させ、約2日かけて米の中で麹菌を繁殖させる。この「製麹」の作業では、麹菌を米に振りかける際の気温、振りかける量など、総合的に杜氏の判断に委ねられることが多く、日本酒の味を決定づける作業になることも。
工程⑦/酛(もと)造り
蒸した米と水に麹、酵母、乳酸菌を加えた酒母造りとも呼ばれ、蒸米に麹・酵母・水を加え、日本酒の発酵のもとを造る。この工程で造られた酒母は、日本酒の原型となる醪のベースになる。また、天然の乳酸を使った酒母を「生酛(きもと)」という。
工程⑧/醪(もろみ)の発酵(並行複発酵)
酛・麹・蒸米・水をタンクに仕込んで培養するが、ゆっくりと発酵させるために麹・蒸米・水は数回に分けて投入し、多くの場合は3回(三段仕込み)で1カ月ほどかけて仕込みをする。この発酵中の状態のものを「醪(もろみ)」という。
工程⑨/上槽(じょうそう)
酒搾りともいわれ、醪を搾って日本酒と酒粕に分けていく。
工程⑩/火入れ
酒が変質しないように低温(60度程度)で熱することで殺菌。同時に酵母の活動を止める。
工程⑪/貯蔵(熟成)
必要に応じて加水してアルコール度数を調整し、低温で寝かせて味を整える。この段階で加水しない酒は、「原酒」と明記されて販売される。
工程⑫/滓引き(おりびき)
「上槽」の過程後の原酒内に残っている米や酵母など、細かいカスを酒の中に沈殿させ、上のほうの高い透明度の部分だけを汲み取る。
工程⑬/ろ過
滓引きによって取り除かれなかった細かいカスを取り除き、さらに透明度を上げる。
工程⑭/瓶詰め
温度や衛生面に注意を払いながら、日本酒を瓶に詰めていく。
人の五感頼りの酒造り。機械はあくまでも道具

現代は、大手の酒造メーカーに限らず中小メーカーでも機械化が進んでいますが、とはいえ機械化は、単純作業や工程の一部に留めているところが多いようです。というのも、製麹が酒造りにとって非常に重要なことであると先述した通り、製麹工程の善し悪しを左右するのが、米の水分量だからです。
米が蒸しあがったときに、麹菌が好む水分量(35%前後)になるよう洗米・浸漬をする必要がありますが、たとえ同じ種類の米であっても、その水分量や水質、水温などさまざまな条件が毎回変化するため、洗米時に米が吸水する量や速度も、そのたびに変化することになります。加えて、その変化によって浸漬時間も変わることになります。その見極めは当然ながら機械では難しく、経験値の高い職人(蔵人・杜氏)の総合的な判断が必要不可欠とされます。
一方で、データ化や単純作業などの工程を機械化することは、酒造りにおける効率化や、職人の労働軽減のためにも重要ですが、指揮をとるのはあくまでも経験値が豊かな“人”であるため、あくまで機械は、効率化を図るための道具として活用されているケースが多いといえます。
道具の洗浄が、日本酒の味を決める
杜氏になる第一歩として、酒蔵、蔵元で習う最初の業務は、徹底した道具の洗浄や施設の清掃であることが一般的とされています。
これは酒蔵、蔵元に限ったことではなく、すべての食品生産工場における共通事項ですが、衛生管理の徹底や、使用する機械・器具等の清掃は、微生物の繁殖を活用している酒造りにとって、単なる雑用ではなく酒の味を決める重要な作業に位置づけられます。
繊細かつ複雑な作業と、的確な判断と感性が求められる日本酒造りでは、日本酒は基本的にタンクや桶(おけ)に蓋(ふた)をせず、醪(もろみ)を育てる「開放発酵」という手法が用いられています。
この手法は、醪の発酵の確認や、発酵をうながしたり温度を均一にするために櫂(かい)と呼ばれる棒でかき混ぜる作業によって行われますが、この工程を行う屋内は無菌状態ではないため、不要な雑菌が混入する可能性があります。そのため、道具やタンクに限らず、施設、人すべてにおいて徹底した衛生的な環境が求められることになります。
ちなみに、昔から納豆は酒造りをする場で厳禁といわれてきました。実際に、納豆菌がどの程度、酒造りに影響するかは科学的に実証されているわけではありませんが、納豆菌が米に繁殖すると、「スベリ麹」と呼ばれるヌメリのある納豆のような麹になってしまうことが判明しており、麹の繁殖を妨げる恐れがあるともいわれているのです。科学的に実証されていないことではあっても、繊細な感性や判断が求められる酒造りの現場ではあらゆる可能性を考慮し、酒造りを損なう危険性を排除するため、仕込み期間中は職人すべてに納豆を食べることを禁止している酒蔵もいまだに多いそう。これは酒造りにおけるちょっとした“トリビア”ですね。
水へのこだわりは、酒そのものの原料だけではない!
水は日本酒の成分の80%を占めており、水が日本酒の味を決める重要なファクターになっていることはいうまでもありませんが、実はこの酒造用に用いる水(酒造用水)は、水道法の水質基準値において厳格に定められています。
この基準は一般水道水のそれよりも厳しく、酒蔵は毎年、都道府県の醸造試験所や食品試験所、酒造指導機関などの公的機関で、酒造用水の監査を受ける必要があります。とくに酒の着色・香味に影響をおよぼす因子となる「鉄」や、日光着色の因子となる「マンガン」の管理には、細心の気配りが求められます。
酒造用水は、酒造の際に用いられる水の総称で、その必要量は米の総重量の約30倍とも50倍ともいわれ、「醸造用水」と「瓶詰用水」の二つに区分され、これらはさらに以下のように分類されて使用されます。
【醸造用水】
●洗米・浸漬用水
●仕込用水(麹・酛・醪に使用)
●雑用用水
【瓶詰用水】
●割水用水(アルコール調整のため原酒に加水する水)
●雑用用水
上記5つの分類のうちの「雑用用水」が、道具・タンクの洗浄や施設内の清掃のほか、ボイラーや瓶の洗浄に用いられる酒造用水です。このように使用する水を細分化している理由は、酒そのものの原料だけに最適な水を用いても、道具や瓶などに酒の品質に影響を与える鉄やマンガン等が含まれていては、酒造りすべてが台無しになってしまう可能性があるからです。
── 少しの妥協や油断が、酒造りすべてに影響をおよぼしてしまう── これほどまでに日本酒造りに繊細さが求められる点も、杜氏が「酒造作家」の異名をもち、「日本酒は芸術的作品」といわれるゆえんといえるでしょう。
米なのにフルーティー! 酵母発酵の秘密

先述したように日本酒造りは、米や発酵の状態は気象条件によって微妙に変わり、味が変化するため、原料の質、工程における秒単位や小数点以下の温度管理によって行われています。そして、それらのタイミングや判断は、杜氏に委ねられているので、その蔵の杜氏が変われば、その酒の味も変わるといわれています。
これは品質が落ちるという意味ではなく、その杜氏の感性や思いによるものであり、この違いをたのしむことも、すべてを機械化せずに造られる日本酒の魅力といえるでしょう。
また、近年海外の人に人気が高まっている「フルーティー(果実味)」な味わいが特徴の日本酒をご存じでしょうか。
フルーティーさに満ちた日本酒は、華やかな香りと爽やかな口当たりで洋食との相性もよく、国内外でも高い人気を誇ります。なかでも名古屋の酒蔵が造る「醸し人九平次(かもしびとくへいじ)」は、ミシュランが認定したフランス・パリの3つ星レストランに、唯一の日本酒として“オンリスト”したことで知られる銘酒です。
でもなぜ、米が原料であり、香りや味を添加していない日本酒に、果実味を感じることができるのでしょうか? ここでは日本酒が醸し出すフルーティーな味わいの秘密をご紹介しましょう。
昨今のフルーティーな香りが特徴とされる日本酒で、よく例えられるフルーティーさというと「洋梨」「メロン」「バナナ」「リンゴ」「白桃」などが挙げられます。これらの風味の正体は、醪の発酵時に清酒酵母によって生成される香りなのですが、この香りを、酒造の世界では「吟醸香(ぎんじょうか)」といい、吟醸酒(吟醸・純米吟醸・大吟醸・純米大吟醸)の生産過程で生成される特有の芳香とされています。日本酒好きの方ならご存じの通り、すっきりとした味わいの日本酒ほど、ワインのような爽やかな風味を感じとることができますね。
このように、吟醸香が果実味にも感じられる理由は、発酵の際に発せられる香気成分にあり、リンゴのような香りがする「カプロン酸エチル」と、バナナのような香りがする「酢酸イソアミル」の二つを主軸に、そこにアルコール度や酸度に変化を加えることによって、リンゴがメロン風味に変化したり、バナナが洋梨風味に変化するのです。
また、吟醸香を発生させるには、精米歩合が低い米で造った醪を約 5〜10度の低温(一般酒は約 8〜15度)で発酵させることが重要です。精米歩合が低いと、酵母がアルコール発酵を行うための栄養素が少なくなり、吟醸香のもとである高級アルコール属が発生しやすくなります。
さらに、香り成分はとても揮散(きさん/香りが微粒子になって広がりやすい作用)しやすい性質をもつため、低温状態でじっくりと発酵させることによってアルコールの揮発性が下がり、香りの成分は蒸発せずに醪の中に蓄積されやすくなる効果が生まれます。この工程では、温度を低く設定し過ぎれば、蒸米は溶けにくく、麹や酵母の活動が抑制されて有機酸(酸味)やアミノ酸(旨味)が減って味のバランスが崩れてしまいます。そのため、杜氏が慎重に工程管理を行い、香りと味わいを絶妙に調整する必要があるのです。
── 「五感を駆使しながら変化する状況を見極め、酒を造り上げる」
── 「バイオテクノロジーの知識で、日本酒の新しい可能性を追い求める」
伝統的でありながらも、最新技術を取り入れた日本酒造りのエキスパート・杜氏。今回はさまざまな視点から日本酒造りについてご紹介してきましたが、伝統と革新を融合させながら、日本酒が製造されていることがおわかりいただけたでしょうか。
これから本格的な冬を迎え、日本酒が美味しい季節がやってきます。グラスに満たされたきらめきを放つ日本酒を堪能しながら、今後も、杜氏が国内外に発信するアーティスティックな日本酒に、大いに期待していきたいものですね。
作業服、ユニフォームを買うならWAWAWORK(ワワワーク)
WAWAWORK(ワワワーク)は、日本最大級の作業服の通販サイトです。
WAWAWORK(ワワワーク)では、オシャレでかっこいい最新の作業服・作業着・ワークウェアから、機能的で便利な定番のワークアイテムまで、幅広い品揃えの商品を激安特価でご提供しているほか、刺繍やオリジナルロゴ入り等のカスタムも対応しております。
作業着、ユニフォームをお探しであれば、通販サイトWOWOWORK(ワワワーク)をぜひご覧ください。webサイト:https://wawawork.work/